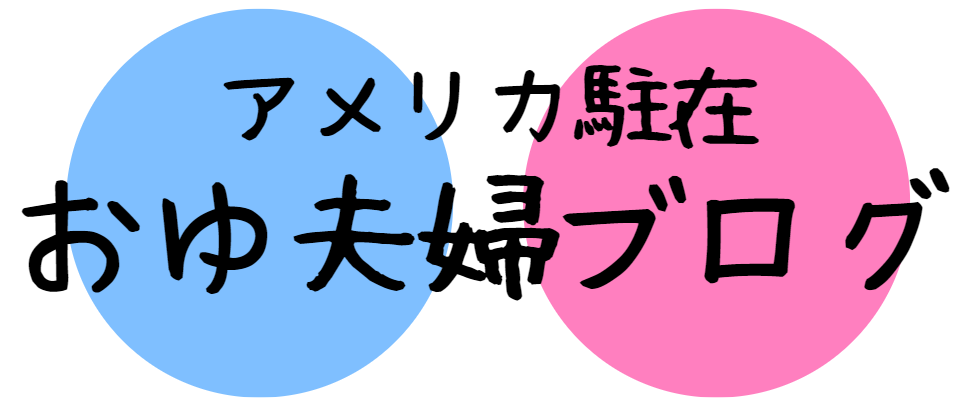こんなお悩みにお答えします。

退職前は漠然とした不安がありましたが、今ではポジティブに考えられています。
この記事でわかること
- 海外赴任に帯同する駐在妻/夫が退職後にすべき手続き
- 海外赴任帯同で退職・移住するタイミング
- 退職して夫の海外赴任に帯同した結果
海外赴任に帯同する駐在妻/夫が退職にあたってすべき手続き
再雇用制度の申請(退職前)
ポイント
- 退職後も元の会社に雇用してもらえる制度
- 制度の利用を希望するなら退職前に人事に申し出る
- 配偶者同行休業制度を採用している会社もある
再雇用制度とは配偶者の出向に帯同するなどの事情で退職せざるを得なくなった従業員を再雇用する制度です。
ジョブリータンやキャリアリターンと呼ぶ企業もあります。
再雇用制度を利用する場合はいったん退職し、本帰国したら採用面接を行った上で再雇用してもらう流れになります。
詳しくはこちら
-
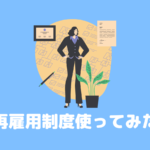
-
退職後の後悔なし!再雇用制度を使って海外赴任に帯同した駐在妻の話
続きを見る
会社によっては代わりに配偶者同行休業制度を採用していることもあります。
配偶者同行休業制度とは退職はせず、休職状態で海外赴任に帯同できる制度です。海外赴任帯同休職と呼ぶ会社もあります。
この場合は本帰国後そのまま同じ会社で働けます。
社会保険料は休職中も払い続けることになります。
どちらも最近は導入している企業が増えていますので希望する場合は人事に確認してみるのをおすすめします。

住民税の納付方法を決める(退職前)
ポイント
- 住民税の支払い方法は普通徴収と一括徴収の2つ
- 一括徴収なら一度に払えて楽
- 支払い方法の希望は退職前に会社に伝えるべし
働き続けていれば納めるはずだった住民税は退職したとしても支払う必要があります。
退職後の住民税の支払い方法は以下の2つです。
- 普通徴収:3か月おきに納付書を使って振り込む
- 一括徴収:退職金や最終月の給料から一括で天引き
普通徴収は基本的に3か月に一度納付書が家に届くのでそれをコンビニなどに持っていって振り込みます。
海外住みの場合は納税管理人を決めて代わりに納めてもらう必要があります。
一方、一括徴収であれば残りの住民税を給料や退職金から一括で天引きしてもらえます。
希望の徴収方法がある場合は会社に伝えておく必要があります。

詳しくはこちら
-

-
海外赴任に帯同する妻は退職後、住民税をどうするべき?【駐在妻】
続きを見る
企業型iDeCoの移管手続き(退職後6か月以内)
ポイント
- 企業型iDeCoは退職後に個人型iDeCoに移換しなくてはいけない
- 退職後、加入しているiDeCoの窓口に海外転出する旨を伝える
- 数日で移換手続き書類が送付されるので記入して返送
会社で企業型iDeCoに加入していた場合は個人型iDeCoに移換する必要があります。
退職したら加入しているiDeCoの問い合わせ窓口に電話して海外転出する旨を伝えます。
そこで今後の流れの説明を受け、手続き書類を送付してもらいます。
数日で書類が届くので必要事項を記入して返送します。
返送後約2か月で移換が承認され、通知書が送られてきます。
詳しくはこちら
-

-
海外赴任に帯同する妻・配偶者が退職後に企業型iDeCoですべき手続き
続きを見る
配偶者の扶養に入る(退職後できるだけすぐ)
ポイント
- 扶養に入ると健康保険料と国民年金保険料を配偶者の会社に払ってもらえる
- 申請前に必要書類そろえるべし
- 健康保険証がない時期に病院に行っても払い過ぎた分を返してもらえる
配偶者の扶養に入ると健康保険料と国民年金保険料を配偶者の会社に払ってもらうことができます。
申請は配偶者が会社で行います。
筆者の時は以下の書類が必要でした。
戸籍謄本(原本)
日本にいる間に忘れずに取得しておきましょう。
3か月以内に取得したものなどの条件があるので、出国直前に取得するのをおすすめします。

退職証明書(原本)
退職前に会社からもらえます。
離職票(写しでも可)
離職票1と2の合計2枚あり、両方とも提出します。

源泉徴収票(写しでも可)
退職後、約1か月で会社から送付されます。

年金手帳の年金番号がわかるページの写し
引っ越し荷物に詰める前に写しを取っておきましょう。

申請は通りましたが、写しを取っておくのが無難です。


雇用保険受給のための手続き(退職後4年以内)
ポイント
- 退職後4年以内に帰国し就活を開始するのなら受給可
- その場合は退職後4年以内に受給期間延長申請が必要
- 駐在妻(夫)は帰国後に受給期間延長申請することになる
駐在妻(夫)でも退職後4年以内に帰国して就活を始めるのなら雇用保険を受給できます。
雇用保険が受給可能な期間は基本的に退職後1年ですが、「配偶者の海外赴任に帯同する」などの理由があれば最大4年まで延長できるのです。
受給期間の延長を希望する場合は退職後4年以内にハローワークで申請する必要があります。
しかし受給期間延長申請ができるのは働くことが困難な状態が30日以上続いてからと決められています。
つまり駐在妻(夫)なら出国後30日以上経ってからでないと受給期間延長申請の権利がありません。
海外にいる間は申請ができないので一時帰国時か本帰国後に延長申請することになります。
雇用保険の受給開始手続きも帰国後4年以内に行います。
詳しくはこちら
-

-
海外赴任に帯同する駐在妻が帰国後に雇用保険(失業保険)を受給する方法
続きを見る
確定申告(退職後5年以内)
ポイント
- 退職した年は年末調整がされていないので自分で確定申告する必要あり
- 退職後5年以内なら必要書類がそろい次第いつでも確定申告できる
- e-Taxでオンライン申請も可能
通常、会社員は年末調整と確定申告で納め過ぎた税金が戻ってきます。
しかし退職して駐在妻・夫になる場合、退職タイミングによってはどちらもできません。
このような人でも退職後5年以内ならいつでも確定申告できます。
申請は税務署またはe-Taxでできます。
必要な書類はこちら。
必要書類
- 確定申告書(税務署にある)(e-Taxなら不要)
- 印鑑(e-Taxなら不要)
- 退職所得した年の給料の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- マイナンバーカードまたは番号確認書類
- 還付金の受け取り口座番号・支店番号
- 医療費や保険など、控除対象の領収書(なければ不要)
マイナンバーカードが必要なので申請できるのは本帰国後です。
やる事は普通の確定申告とほぼ同じです。
唯一の違いは年末調整も自分で行う必要がある点です。とはいえ源泉徴収票を見ながら指示に従って必要情報を埋めればOKです。
準確定申告をする必要があると記載されているサイトもありますが、筆者が税務署に行って確認したところ、準確定申告は故人の確定申告を代わりに行うことであり、駐在に帯同した家族は普通の確定申告を行うように言われました。
(帰国後追記)筆者は2年で本帰国したので、マイナンバーカードを手に入れた後、e-Taxで退職した年の確定申告をしました。結果、5万円以上還付されました。
海外赴任帯同で退職・移住するタイミング
退職と移住のタイミング、迷いますよね…
会社の規則や手続きなど色々な要素が関わってきます。
ここでは退職と移住のタイミングを決める要素を洗い出した上で、筆者の体験談を紹介します。
少しでも参考になれば幸いです。
退職・移住タイミングを決める要因
退職の申し出時期
今日明日では退職できないと思うので、いつまでに退職を申し出るべきか会社に確認しておく必要があります。

仕事の都合
仕事のキリのいいタイミングで移住するのが理想ですよね。
自分にとっていいタイミングでも上長に相談すると「〇月まではいてほしいな」と言われるかもしれません。
希望を決めた上で上長と話し合ってみてください。
有給の消化具合
できるだけ有給を消化してから渡航したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
どれだけ有休を消化するのかも渡航タイミングに関わります。

ボーナスの時期
あと数か月粘ればボーナスがもらえる場合は有給を消化しつつ在籍し続けるのもアリです。

帯同していいタイミング
配偶者の海外赴任と同時に渡航できるのか、それとも時期を遅らせる必要があるのかは配偶者の会社に確認してみてください。

退職後の手続き
退職後の手続きに必要な離職票と源泉徴収票は退職後数週間から数か月以内に会社から送付されます。
iDeCoの移換承認通知書はiDeCoの移換申請をしてから約2か月で送られてきます。
すべて自分で受け取る場合は退職後2か月以上は日本にいる必要があります。
代理で書類を受け取ったり、写しを送ってくれたりする人が日本にいればもっと早く渡航できます。

必要な手続きがすべて完了できるかは事前に考えておきましょう。
筆者が海外赴任帯同と退職・移住タイミングを決めた経緯
海外赴任の話をもらったのは赴任開始の7カ月前くらいです。
初め聞いたときは驚いて反対していましたが、数か月悩んだ結果、帯同することを決断しました。
主な理由は以下です。
- 夫は来てほしいと言っていた
- 結婚間もない
- 子供がいなくて身軽
- 旅行は好き
- 海外に住むなんて二度できない貴重な体験

帰国後の職は心配でしたが、再雇用制度を利用できたので安心して決められました。
退職や移住のタイミングは「できるだけ早く渡航したい」ということを軸に考えました。
実際に配偶者の移住が許されてすぐに移住しました。
退職は移住の2週間前にしました。退職後に色々と手続きがあるかと思って即渡航するのは避けました。

有給途中に移住するのはアリ?
海外赴任帯同を控えている方の中には

と思う方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、海外移住は退職してから行うのを強くおすすめします。
理由は退職前に住民票を海外に移してしまうと渡航先の国で税金の支払い義務が発生するかもしれないからです。
そこまで面倒を見てくれる会社ならいいですが、そうでなければ自分で税金を計算して納める必要があるかもしれません。
また、就労許可がないビザにも関わらず就職状態にあるとビザを取り消される恐れもあります。
どうしてもという方は有給消化中に旅行として渡航し、退職後に帰国して役所で海外転出手続きをすれば問題ないかと思います。(あくまで自己責任でお願いします)
退職して夫の海外赴任に帯同した結果
退職前に不安だったこと
退職前に不安だったのは主に以下の3つです。
- 帰国後に就職できるのか
- 英語は大丈夫か
- 海外生活をうまくやっていけるのか
多くの方が同じことを不安に思っているのではないでしょうか?
ただ、駐在妻になって1年経った今ではどれもあまり心配していません。
むしろ駐在妻になって良かったと思っています。
ポジティブに考えられた理由
帰国後の就職についてはありがたいことに再雇用制度を利用できたのであまり心配せずに済みました。
退職するという事実が漠然と不安だった時期もありましたがもう慣れました(笑)
英語は最初、挨拶すら聞き取れませんでした。
ですが渡米前からちょくちょく音読や英会話を頑張った結果、レストランでのやり取りなど基礎的な会話はできるようになりました。
働くのならもっと話せる必要がありますが、生活する分にはそのレベルで十分です。
日本語訛りMAXで話していても店員さんは普通に対応してくれます。
関連記事
-

-
アメリカ駐在妻が英語を話せるようになった勉強方法【上達必至】
続きを見る
筆者は退職を機にブログを2つ始め、働いていた時と同じくらいの時間をブログに使っています。
本ブログは思い出作りしつつ誰かの役に立てばいいなと思って書いています。将来的に収益化もできたらいいなと思っています。
映画やドラマを漁るという過ごし方もありますが、消費するばかりだと社会との繋がりを感じられずに病んでしまう駐在妻さんが多いです。
クリエイティブなことに励んでいると日々が充実する気がします。
関連記事
-

-
駐在妻が働けない理由と仕事禁止でもできる在宅ワーク4選
続きを見る
同時に仕事から離れることで自分のキャリアを見直すきっかけになりました。
筆者はブログを書く生活をしている間にフルリモートで働きたいという思いが湧いてきました。
フルリモートであれば家族との時間を増やせそうですし、ワークスタイルが自分に合っていそうです。
そのためにフルリモートでできそうなプログラミング言語を学んだり、フリーランスの働き方を調べたりしています。

海外移住が思わず人生を変えるきっかけになるかもしれませんよ。
おわりに:ぜひ退職後の生活も楽しんでください
退職後にやることは多いですが、数か月で落ち着いて赴任先での日常生活が始まります。
海外で生活するなんてなかなかできない経験ですから、ぜひ旅行に行ったり働いていた時にはできなかったことに挑戦したりしてみてください。
自分にとって幸せな生き方を考え直すきっかけになるかもしれませんよ。
海外移住時の準備全般については以下の記事で解説しています。
海外移住準備まとめ
-

-
【海外赴任準備】経験者が教えるアメリカ駐在前にやることリスト
続きを見る